 フリーランス
フリーランス「フリーランスの確定申告、どうやって節税すればいいの?」「経費にできるものって何?」「知らないうちに税金を払いすぎているかも…」



今回はこんなお悩みにお答えしていくで〜!
実は、フリーランスの確定申告には、知っているだけで数万円〜数十万円もの節税につながる控除や経費計上の方法が存在します。
本記事では、フリーランスが今すぐ使える5つの節税術を、具体的な計上方法や注意点とともに詳しく解説します。
フリーランスの確定申告とは?基礎知識を押さえよう


確定申告が必要なフリーランスの条件
フリーランスとして働く場合、基本的に年間の所得が48万円を超えると確定申告が必要になります。所得とは「収入 – 経費」で計算される金額です。
たとえば、年間収入が300万円で経費が100万円の場合、所得は200万円となり、確定申告が必要です。副業でフリーランス活動をしている会社員の場合は、副業所得が20万円を超えると申告義務が発生します。
白色申告と青色申告の違い
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
白色申告は手続きが簡単ですが、特別な控除がありません。一方、青色申告は複式簿記での記帳が必要ですが、最大65万円の特別控除を受けられるため、節税効果が非常に高いです。
青色申告を選択するには、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
確定申告の期限と提出方法
確定申告の期限は、毎年2月16日から3月15日までです。この期間内に前年1月1日から12月31日までの所得を申告します。
提出方法は、税務署への直接持参、郵送、e-Taxによる電子申告の3つがあります。特にe-Taxは自宅から手続きができ、青色申告特別控除も最大額の65万円が適用されるためおすすめです。



確定申告は必ず青色申告で提出しよな!節税効果が圧倒的に高いから🙌難しく考える必要ない(笑)最初は青色申告で出してたらOK👍
【節税術1】青色申告特別控除で最大65万円控除
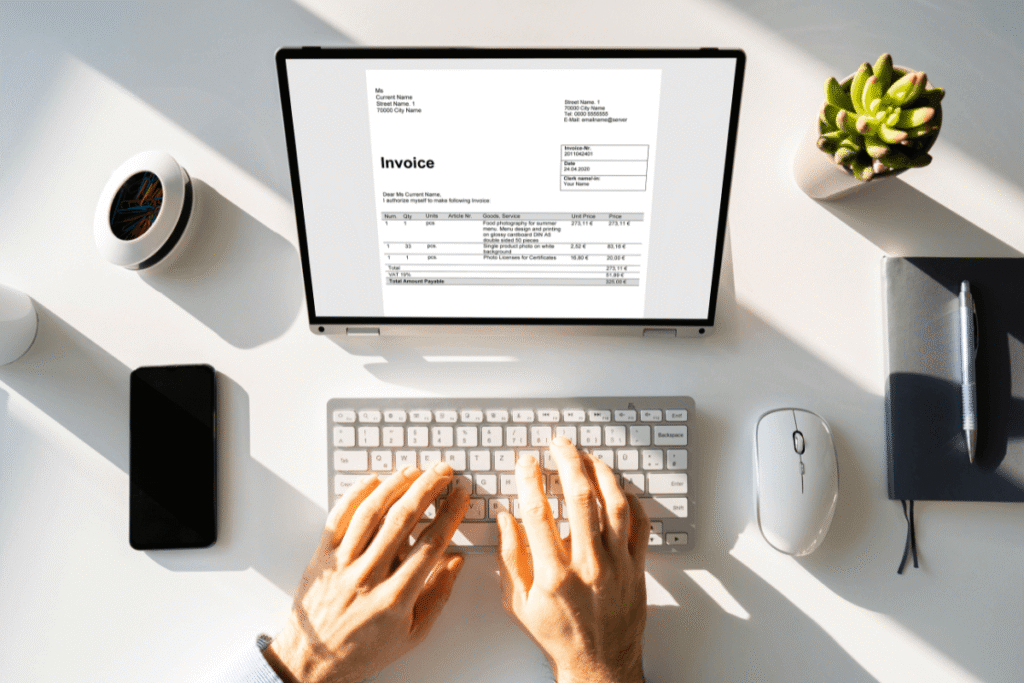
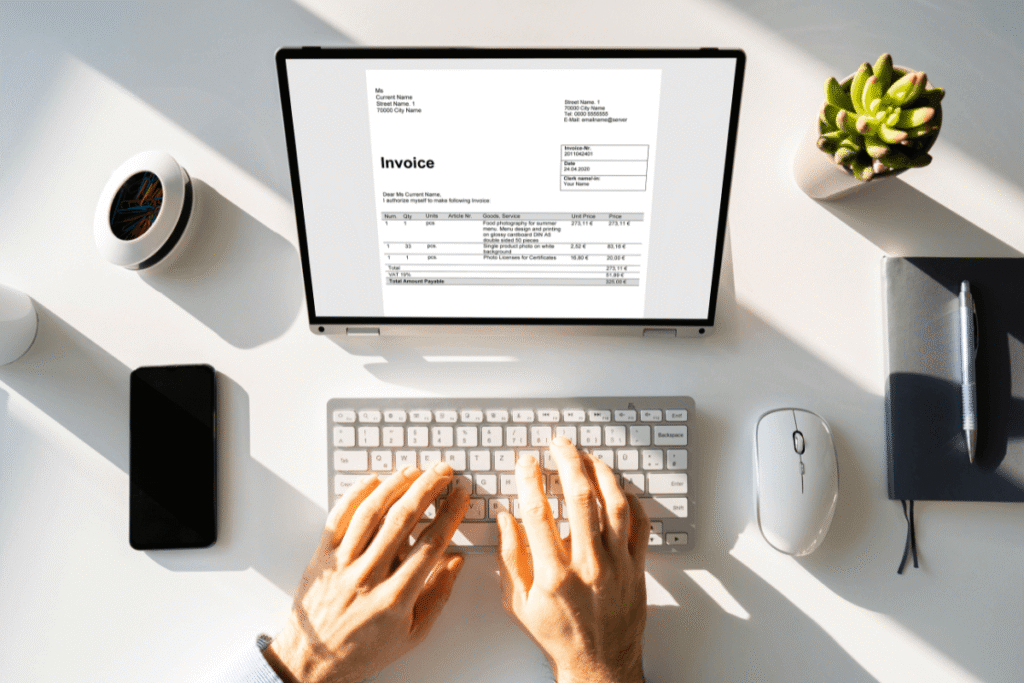
青色申告特別控除とは
青色申告特別控除は、青色申告を行う事業者が受けられる最も効果的な節税制度の一つです。所得から最大65万円を控除できるため、課税所得を大幅に減らすことができます。
たとえば所得が400万円の場合、65万円控除を受けると課税所得は335万円になり、税率20%なら約13万円もの税金を節約できる計算になります。
65万円控除を受けるための条件
複式簿記での記帳が必須
65万円の特別控除を受けるには、複式簿記での正確な記帳が必要です。複式簿記とは、取引を「借方」と「貸方」の2つの側面から記録する方法です。
初心者には難しく感じるかもしれませんが、会計ソフト(freee、マネーフォワード、弥生会計など)を使えば、自動的に複式簿記形式で記帳してくれるため安心です。
e-Taxでの電子申告が有利
2020年分の確定申告から、65万円控除を受けるにはe-Taxでの電子申告または電子帳簿保存が条件となりました。紙で提出する場合は55万円控除となります。
e-Taxはマイナンバーカードとカードリーダー、またはスマートフォンがあれば利用できます。
青色申告承認申請書の提出期限
青色申告を始めるには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
新規開業の場合は開業日から2ヶ月以内、すでに事業を行っている場合は青色申告を始めたい年の3月15日までに提出しましょう。



基本的に帳簿は会計ソフト使えばめちゃくちゃ楽👍今までなら紙媒体やExcelで管理するのが当たり前やったけど、初心者は間違いなく会計ソフトが良い🙌俺はfreee、マネーフォワード、弥生会計の無料期間を全て使い倒した(笑)そこから自分が使いやすいソフトを見つけたらOK👌
【節税術2】経費を正しく計上して課税所得を減らす


フリーランスが経費にできる主な項目
通信費・光熱費の家事按分
自宅で仕事をしているフリーランスは、インターネット代や電気代などを経費として計上できます。ただし、プライベートでも使用している場合は「家事按分」という方法で、仕事に使った割合だけを経費にします。
たとえば、1日8時間を仕事に使っているなら、約30%(8時間÷24時間)を経費として計上できます。
交通費・交際費の計上方法
打ち合わせや営業活動のための交通費、クライアントとの食事代なども経費になります。電車代、タクシー代、駐車場代、高速道路代などはすべて計上可能です。
交際費は、仕事に関連する飲食や贈答品などが対象です。ただし、誰と、何の目的で使ったのかを記録しておくことが重要です。
書籍代・セミナー代などの自己投資
仕事に関連する書籍、オンライン教材、セミナー参加費なども経費になります。プログラマーならプログラミング本やUdemy講座、デザイナーならデザイン関連の書籍やAdobe Creative Cloudの月額費用なども対象です。
経費計上時の注意点とレシート管理
経費として認められるには、レシートや領収書などの証拠書類が必要です。これらは7年間保存する義務があります。
クレジットカードの明細だけでは不十分な場合もあるため、できるだけレシートや領収書を保管しましょう。スマホアプリで写真を撮って管理すると便利です。
家賃の按分で節税効果を高める
自宅の一部を事業用に使っている場合、家賃も経費にできます。たとえば、50平米の自宅のうち10平米を仕事スペースとして使っているなら、家賃の20%を経費計上できます。
月10万円の家賃なら、年間24万円を経費にでき、税率20%なら約4.8万円の節税になります。



フリーランスになると、基本的に経費にできるものが多い!最初のうちは何を経費にできるかって全ては把握できんと思うから、とりあえず、レシートと領収書は常にもらっておこう(笑)ただ、プライベートで使ったお金は経費にできんから、そこだけは要注意🙌
【節税術3】小規模企業共済で掛金を全額控除


小規模企業共済とは
小規模企業共済は、フリーランスや小規模事業者のための退職金制度です。独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しており、毎月の掛金を積み立てることで、廃業時や退職時にまとまった資金を受け取れます。
最大の魅力は、掛金が全額所得控除の対象になることです。
掛金の設定と全額所得控除のメリット
掛金は月額1,000円から7万円まで、500円単位で自由に設定できます。年間最大84万円を所得から控除できるため、節税効果は絶大です。
たとえば、月3万円(年間36万円)を掛けた場合、税率20%なら約7.2万円の節税になります。さらに、掛金は将来自分に戻ってくるため、貯蓄と節税を同時に実現できます。
加入条件と申込方法
加入条件は、従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主または会社役員です。フリーランスのほとんどが該当します。
申込は、商工会議所や金融機関、中小機構のウェブサイトから可能です。加入には確定申告書の控えなどが必要になります。



フリーランスになったら企業と違うのが退職金が出ないこと!ただ、この小規模企業共済は、毎月積み立てをして、廃業した際にまとまった資金がもらえちゃうのよ🤟貯蓄と節税にもなるから、やらん手はない(笑)
【節税術4】iDeCo(個人型確定拠出年金)で所得控除を最大化


iDeCoの仕組みと節税効果
iDeCoは自分で運用する年金制度で、掛金、運用益、受取時のすべてで税制優遇を受けられます。特に掛金が全額所得控除になる点が大きなメリットです。
60歳まで引き出せないというデメリットはありますが、老後資金の準備と節税を両立できる制度です。
フリーランスの掛金上限額
フリーランス(国民年金の第1号被保険者)の場合、iDeCoの掛金上限は月額6.8万円(年間81.6万円)です。ただし、国民年金基金の掛金と合算での上限となります。
月2万円を積み立てた場合、年間24万円の所得控除となり、税率20%なら約4.8万円の節税になります。
iDeCoと小規模企業共済の併用戦略
iDeCoと小規模企業共済は併用可能です。両方を最大限活用すれば、年間165.6万円の所得控除を受けられます。
ただし、掛金を支払う余裕があるかを考慮し、まずは小規模企業共済から始めて、余裕ができたらiDeCoを追加するという戦略がおすすめです。



iDeCoは掛金が全額所得控除になるのだ!老後資金と節税を両立できるからかなり大きい🙌しかも、さっきの小規模企業共済と併用ができるから、どっちも利用するしかないよね(笑)これも必須やで🤟
【節税術5】ふるさと納税で住民税を節税


ふるさと納税の仕組み
ふるさと納税は、自治体に寄附をすることで、寄附額から2,000円を引いた金額が所得税と住民税から控除される制度です。さらに、返礼品として地域の特産品なども受け取れます。
実質2,000円の負担で様々な返礼品がもらえるため、非常にお得な制度です。
フリーランスの控除上限額の計算方法
ふるさと納税には控除上限額があり、これを超えると自己負担が増えます。上限額は年収や家族構成によって異なります。
たとえば、独身で年収500万円の場合、上限額は約6万円です。各ふるさと納税サイトにシミュレーターがあるので、事前に確認しましょう。
ワンストップ特例と確定申告の違い
ふるさと納税で控除を受けるには、確定申告が必要です。ただし、寄附先が5自治体以内であれば「ワンストップ特例制度」を使うことで確定申告が不要になります。
しかし、フリーランスは元々確定申告が必要なため、通常の確定申告時に寄附金控除として申告すればOKです。



ふるさと納税も節税としてめちゃいいし、実質2,000円で色んな返礼品がもらえるのだ🤟とにかく節税対策は恩恵をかなり得れるから、片っ端から全部やろな👍
確定申告で注意すべきポイント
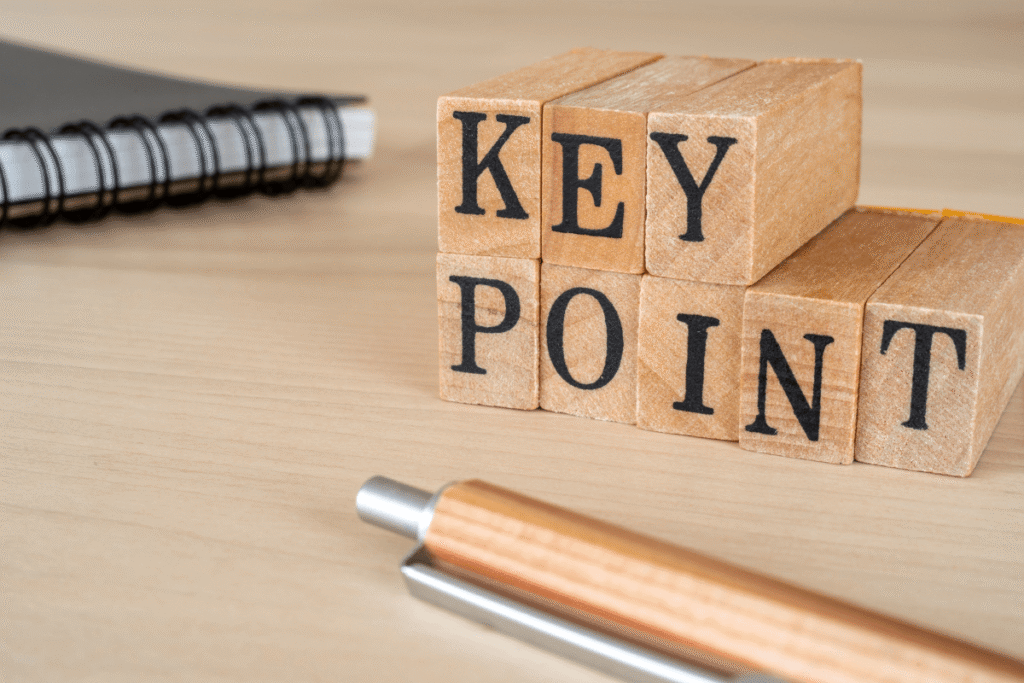
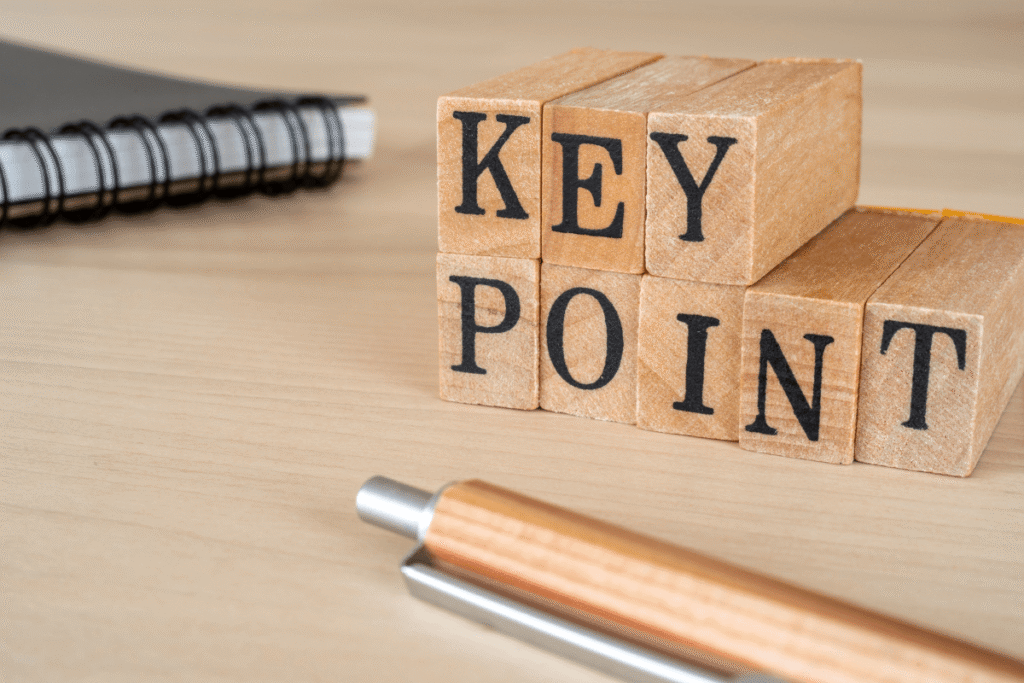
経費の根拠資料は7年間保存
税務調査に備えて、領収書やレシートなどの経費の根拠資料は7年間保存する義務があります。紙での保管が原則ですが、スキャンやスマホ撮影での電子保存も認められています。
クラウド会計ソフトを使えば、撮影した領収書を自動で仕訳してくれるため便利です。
売上の計上漏れに注意
特に年末年始の売上は計上漏れが起きやすいので注意が必要です。12月に仕事をして翌年1月に入金された場合でも、原則として12月の売上として計上します。
ただし、小規模事業者は「現金主義」も選択でき、この場合は入金時に売上計上できます。
税務調査に備えた記帳の重要性
税務調査は誰にでも来る可能性があります。日頃から正確な記帳を心がけ、経費の根拠を明確にしておくことが大切です。
不安な場合は、税理士に相談するのも一つの方法です。記帳代行や税務相談を依頼すれば、安心して事業に集中できます。



今はペーパーレス化してるから、ほとんど電子での管理が主流になってきてる!紙での保存は紛失や劣化、保管場所を用意したりとデメリットが多い😅やから基本的には、全て電子での管理にしていこな🙌記帳で分からんことがあったら税理士に聞くでもええけど、今はAIが教えてくれる(笑)できるだけお金はかけんように、自分でできることは頑張ろな👍
よくある質問(FAQ)
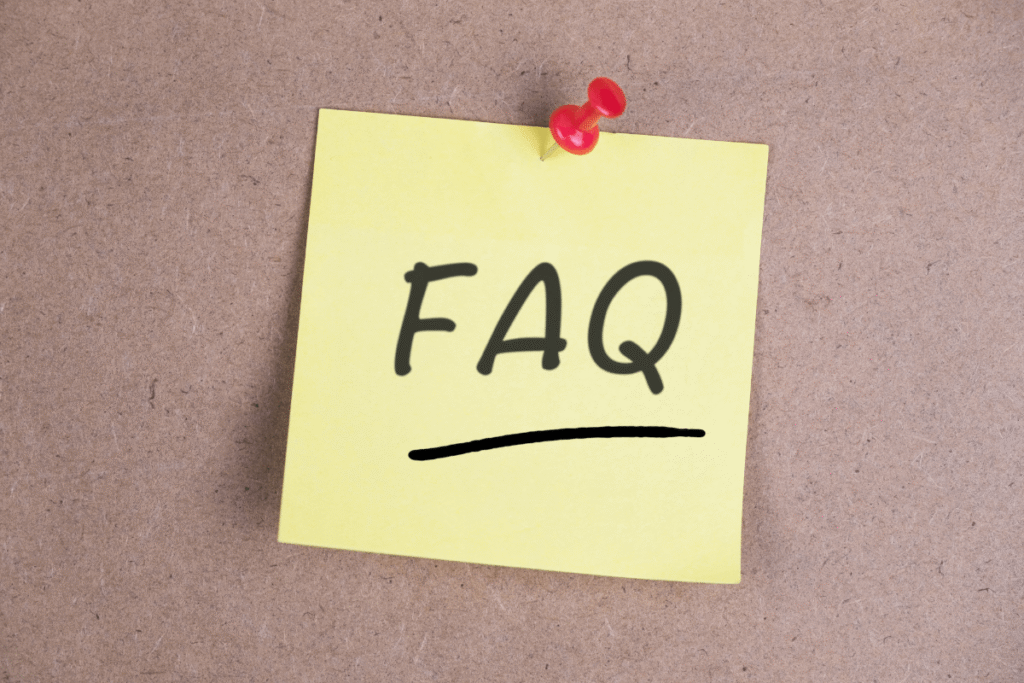
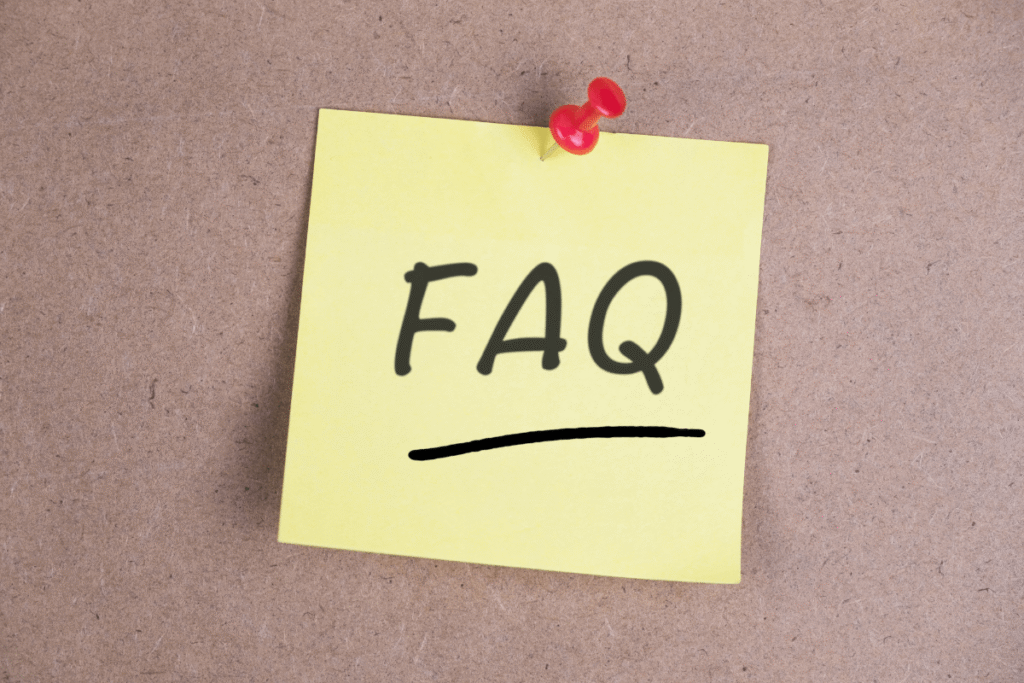
- 確定申告をしないとどうなりますか?
-
確定申告をしないと、無申告加算税(最大20%)や延滞税が課されます。悪質な場合は刑事罰の対象にもなるため、必ず期限内に申告しましょう。
- 青色申告は初心者でもできますか?
-
会計ソフトを使えば初心者でも問題なく青色申告できます。freeeやマネーフォワードなどのソフトは、簿記の知識がなくても簡単に記帳できる設計になっています。
- 経費にできるか判断が難しい支出はどうすればいい?
-
「事業に直接関連しているか」が判断基準です。迷う場合は税理士に相談するか、国税庁の相談窓口を利用しましょう。グレーゾーンの支出は避けるのが無難です。
- 確定申告を税理士に依頼した方がいいですか?
-
事業規模が大きい場合や時間がない場合は税理士への依頼がおすすめです。費用は年間10〜30万円程度ですが、節税効果や時間の節約を考えると十分元が取れます。
- iDeCoと小規模企業共済、どちらを優先すべきですか?
-
一般的には小規模企業共済を優先するのがおすすめです。解約時の受取条件が柔軟で、事業資金としても活用できるためです。余裕があれば両方を併用しましょう。
まとめ:フリーランスの確定申告で賢く節税しよう


いかがでしたか?今回は、フリーランスが実践すべき5つの節税術を解説しました。最後に重要なポイントをまとめます。
本記事の要点:
- 青色申告特別控除(最大65万円)
- 複式簿記とe-Tax利用で最大控除を受けられる
- 会計ソフトを使えば初心者でも対応可能
- 事前の承認申請が必要(3月15日までに提出)
- 経費の正しい計上
- 通信費、光熱費、家賃などは家事按分で経費化
- レシートや領収書は7年間保存が義務
- 仕事関連の支出は積極的に経費計上
- 小規模企業共済(年間最大84万円控除)
- 掛金が全額所得控除になる
- 廃業時に退職金として受け取れる
- 月1,000円から始められる
- iDeCo(年間最大81.6万円控除)
- 老後資金の準備と節税を同時実現
- 60歳まで引き出せないので注意
- 小規模企業共済との併用が効果的
- ふるさと納税
- 実質2,000円で返礼品がもらえる
- 控除上限額の確認が重要
- 確定申告時に寄附金控除として申告
今すぐ始められるアクション:
- 青色申告承認申請書の提出(まだの方)
- 会計ソフトの導入と日々の記帳習慣
- 小規模企業共済またはiDeCoへの加入検討
- 経費になる支出の洗い出しとレシート管理
フリーランスの節税は、知識と実行力が全てです。この5つの節税術を実践すれば、年間数十万円の節税も十分可能です。
不安な点や複雑な手続きがある場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。賢く節税して、事業をさらに成長させていきましょう!
プロとして副業やフリーランスで活動していきたい方は、
弊社が運営している、フリーランス総合スクール「rockSchool」までお気軽にご相談くださいね!
公式LINE登録はこちら➡️https://lin.ee/mBbCUqB
実際のオフライン授業の風景はYouTubeで発信しています↓↓
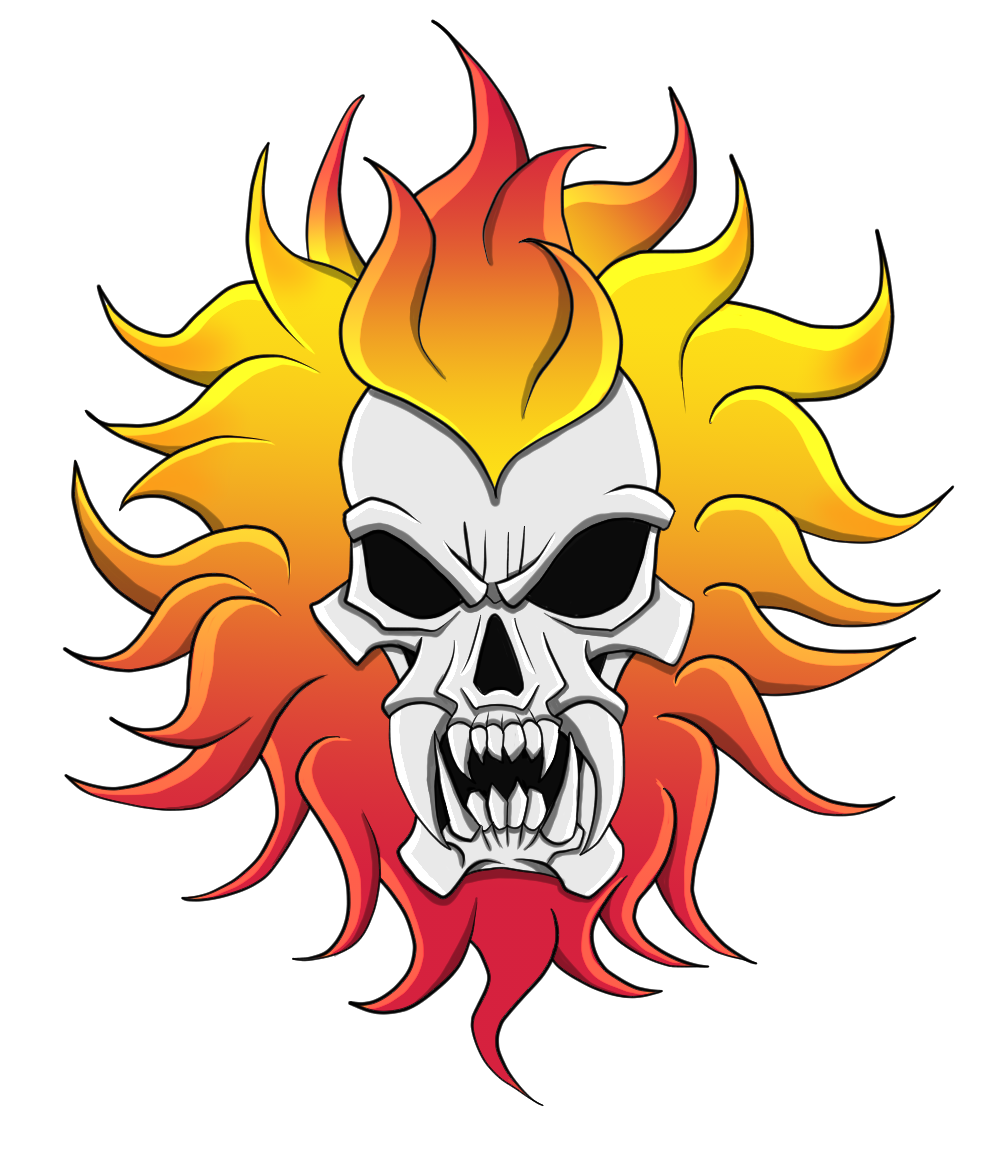
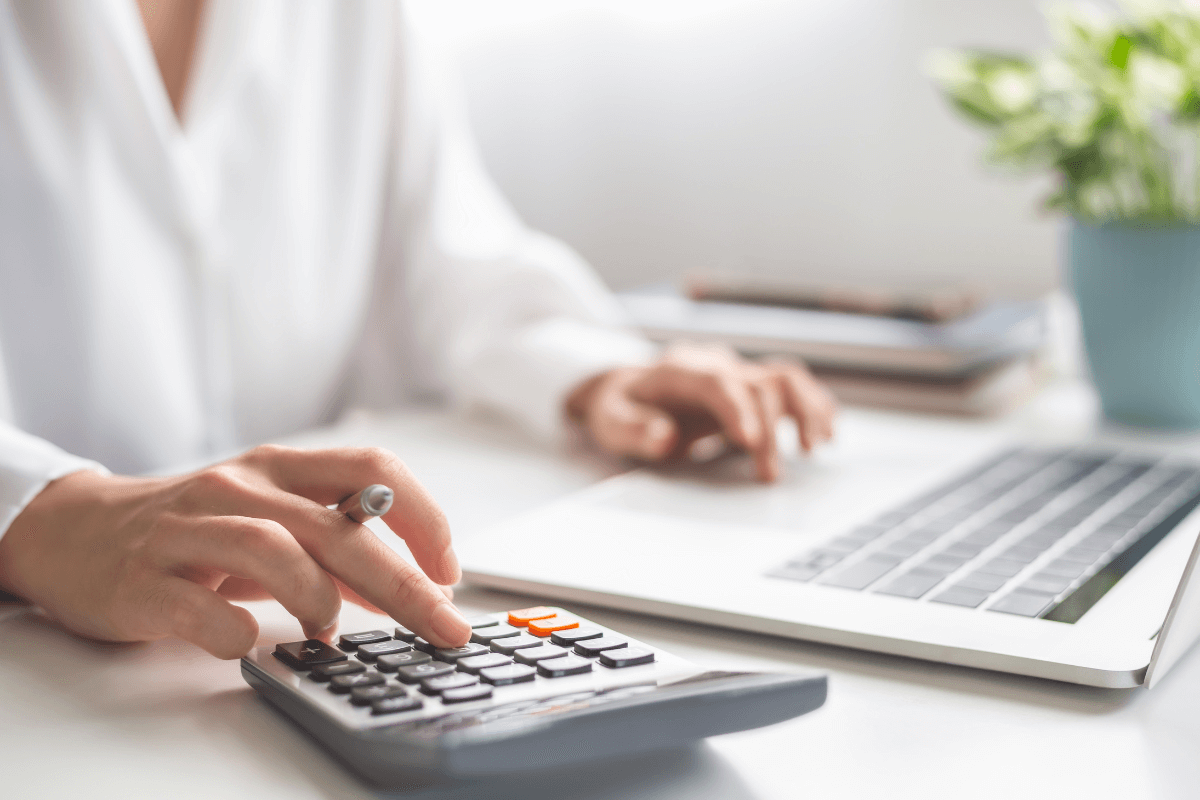

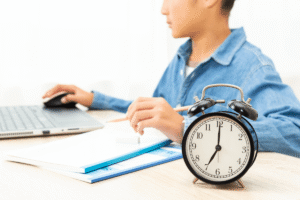
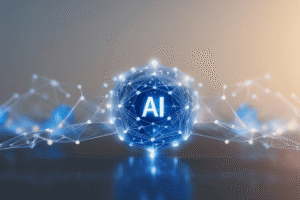




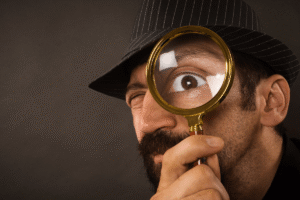
コメント